本記事は、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ(レッチリ、Red Hot Chili Peppers)2010年代の名曲を解説します。
※目次もご活用くださいませ。
1.10年代の5曲
Red Hot Chili Peppers(以下レッチリ)は10年代にアルバムを2枚リリースしています。
10年代はレッチリ史上最も「オルタナティブ」な音楽性。
下記は、「オルタナティブ」で、かつ、独創的な名曲5曲になります。
- Monarchy of Roses
- Brendan’s Death Song
- Dark Necessities
- Dreams of a Samurai
- Goodbye Angels
では、それぞれ見ていきましょう!
2.Monarchy of Roses

まず、1曲目は、Monarchy of Roses。
Monarchy of Rosesは、ジョシュの個性とレッチリらしさがせめぎ合っていてスリリング。
| タイトル | 「モナーキー・オブ・ローゼズ」(Monarchy of Roses) |
| 収録アルバム | 『アイム・ウィズ・ユー』(I’m with You) |
| 作曲 | アンソニー・キーディス、フリー、ジョシュ・クリングホッファー、チャド・スミス |
| 演奏メンバー | アンソニー・キーディス(v)、フリー(b)、ジョシュ・クリングホッファー(g)、チャド・スミス(ds) |
| プロデュース | リック・ルービン |
聴きどころ
Monarchy of Rosesの聴きどころは、レッチリ流ディスコ・グルーヴとアヴァンギャルドな轟音ギターとのスリリングなせめぎ合いにあります。
この曲には、ポジティブなパワーがあふれている。
ちなみに、本作のMVアートワークは、レイモンド・ペティボンによる作品。
レイモンド・ペティボンは、ブラック・フラッグや、ソニック・ユース、近年はディオールとのコラボでも話題になったNYのアーティストです。
下記は、『I’m with You World Tour』前、2011年8月24日のロサンゼルス公演でのMonarchy of Roses。
ライブでも、ジョシュの破壊的な感性と、リズム隊の強力なグルーヴがフィーチャーされています。
こちらは、『I’m with You World Tour』後半の、2013年3月3日メキシコ公演でのMonarchy of Roses。
ロサンゼルス公演よりも、楽曲の完成度が上がっています。
*おまけ*(カラオケ)
下記は、アメリカCBSの人気プログラム『The Late Late Show』のジェームズ・コーデンが、ゲストと車内でカラオケを楽しむ人気コーナー『Carpool Karaoke』にレッチリが出演した際の映像。
円熟のおふざけをお楽しみください。
3.Brendan’s Death Song

つぎに、2曲目は、Brendan’s Death Song。
Brendan’s Death Songは、親友への思いをポジティブに歌うアンソニーらしさが清々しくてかっこいいから。元気になるんです。この曲。
ちなみに、ブレンダンとはブレンダン・マレン氏のことで、レッチリ公式の伝記『レッド・ホット・チリ・ペッパーズ オフィシャル・バイオグラフィ』の著者。
ブレンダン・マレン氏は、LAパンクシーンにおける重要人物です。
『レッド・ホット・チリ・ペッパーズ オフィシャル・バイオグラフィ』はブレンダン・マレン氏と、ジョン・キーディス(アンソニーの実父)による共著。
2009年10月12日に亡くなったブレンダン・マレン氏の死を歌った楽曲がこのBrendan’s Death Songです。
| タイトル | 「ブレンダンズ・デス・ソング」(Brendan’s Death Song) |
| 収録アルバム | 『アイム・ウィズ・ユー』(I’m with You) |
| 作曲 | アンソニー・キーディス、フリー、ジョシュ・クリングホッファー、チャド・スミス |
| 演奏メンバー | アンソニー・キーディス(v)、フリー(b)、ジョシュ・クリングホッファー(g)、チャド・スミス(ds) |
| プロデュース | リック・ルービン |
聴きどころ
Brendan’s Death Songの聴きどころは、前向きな歌詞にあります。
「I said yeah」と鼓舞するアンソニーらしいポジティブな歌詞がパワーを与えます。
祝祭的でもあり、MVで描かれる葬列のシーンもまるでカーニバルのように華やかです。
下記は、『I’m with You World Tour』前半の、2011年10月7日のドイツ公演でのBrendan’s Death Song。
ジョシュはセミアコを使い、あくまでアンソニーの力強いボーカルをフィーチャーしているところがステキです。
こちらは、『I’m with You World Tour』中盤に参加した、2012年8月4日のロラパルーザ・シカゴ公演でのBrendan’s Death Song。
さっきの約1年後のライブ。
ギターのアレンジが結構サイケになってます。
ジョシュらしくてかっこいい。
*おまけ*(感性)
下記は、ジョシュのコーラスを入れたBrendan’s Death Songのオケ音源。
こうして聴くと結構シューゲイザー的ですね。
ジョシュのコーラスワークは、マイブラぽくもあって、甘酸っぱい。
ジョシュのこういう感性は今までのレッチリにはなかった側面。
かなりジョシュをフィーチャーしてたことが伺えますね。
4.Dark Necessities

そして、3曲目は、Dark Necessities。
Dark Necessitiesでは、過去の自分を否定せず、強がることもないアンソニーをさらけ出しています。
音楽的にも、I’m with Youで得た課題を乗り越えたレッチリ。
I’m with Youよりもメンバーの絆も深まり、意見をとことんぶつけ合うことで制作に遠慮がなくなった。
プロデューサーがデンジャー・マウスになったのも新たな刺激になっています。
| タイトル | 「ダーク・ネセスティーズ」(Dark Necessities) |
| 収録アルバム | 『ザ・ゲッタウェイ』(The Getaway) |
| 作曲 | アンソニー・キーディス、フリー、ジョシュ・クリングホッファー、チャド・スミス |
| 演奏メンバー | アンソニー・キーディス(v)、フリー(b)、ジョシュ・クリングホッファー(g)、チャド・スミス(ds) |
| プロデュース | デンジャー・マウス |
聴きどころ
Dark Necessitiesの聴きどころは、切なさが詰まった強がらないアンソニーのむき出しの歌詞です。
そして、その世界観を支えるジョシュらしいアヴァンギャルドなギターフレーズ。
更に、フリーらしいグルーヴィーな円熟したスラップ・ベース。
下記は、2018年に出演したロラパルーザ・チリ公演でのDark Necessities。
かっこいい。。
下記は、2019年リオ・デ・ジャネイロで開催されたRock In Rioへ出演した際のDark Necessities。
ジョシュと歩んだ10年はあっという間だった。
*おまけ*(ギア)
下記は、ずらりと並ぶジョシュのコンパクトエフェクターたち。
ジョンと共通するエフェクターも多いですが、ジョシュならではのトリッキーなサウンドメイクも見受けられます。
「ダーク・ネセスティーズ」で特徴的なこのヘリコプターサウンド。
この設定は、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのトム・モレロも使ってました。
ジョシュはこのサウンドを、「カオスなムード」と、「現代的な感触」の演出に巧みに落とし込んでいます。
5.Dreams of a Samurai

さらに、4曲目は、Dreams of a Samurai。
Dreams of a Samuraiは、もはや一聴してレッチリとはわからないような、荘厳な世界観。
その世界観に、ベースが入り、ドラムが入り、ボーカルが入り、ギターが入ると、更に無限の広がっていく空間。
| タイトル | 「ドリームス・オブ・ア・サムライ」(Dreams of a Samurai) |
| 収録アルバム | 『ザ・ゲッタウェイ』(The Getaway) |
| 作曲 | アンソニー・キーディス、フリー、ジョシュ・クリングホッファー、チャド・スミス |
| 演奏メンバー | アンソニー・キーディス(v)、フリー(b)、ジョシュ・クリングホッファー(g)、チャド・スミス(ds) |
| プロデュース | デンジャー・マウス |
聴きどころ
Dreams of a Samuraiの聴きどころは、なんといっても、空間的な広がりのあるグルーヴにあります。
淡々と響くピアノと荒々しいドラムが生むカオスもこの曲の魅力。
By the Way収録のTimeに近い世界観ですが、Dreams of a Samuraiからは、ある種の「覚悟」を感じます。
ちなみに、The Getaway全体にある、空間の広がりを感じさせるサウンドは、サウンドエンジニアに参加しているナイジェル・ゴッドリッチの手腕も大きく影響しています。
ナイジェル・ゴッドリッチはレディオヘッドの多くの作品に関わってきたエンジニアで、第六のレディオヘッド・メンバーとも言われている人物です。
近代的で奥行きの広がりあるサウンドメイクが、悶絶級にかっこいい。
下記は、The Getaway World Tourの中盤、2017年7月15日に出演した『International Festival in Benicassim』のスペイン公演でのDreams of a Samurai。
超鳥肌です。
かっけえ。。
ライブアレンジでも、ピアノが荘厳な世界観を描き、ギターとベースが織りなすプログレサウンドと、タイトでパワフルなドラムが、広がりのあるカオスを作っています。
独特のカオスの中を、アンソニーのリリックが宙に舞う感じが本当鳥肌。
下記は、The Getaway World Tour終了後、2019年2月25日にオーストラリアのブリスベン公演でのDreams of a Samurai。
このメンバーなくして、この演奏は生まれなかったであろう神がかり的な演奏。
浮遊するカオス、サビで明確な姿に変容する様、「I got a metamorphosis samurai」というリリックとシンクロします。
メンバーの個性がそのままカオスを描き、時の流れとともに一斉に一つの目的に向かう構成が見事すぎてコワイ。
*おまけ*(寛大)
下記は、The Getawayリリース時のワーナーのプロモーション。
インタビューでアンソニーが回答している通り、新メンバーと向き合うにはいつだって時間が掛かる。
作品を作るには実験をする時間が必要というのは、まさにジョンの時も、ジョシュの時も同様だった。
寛容で前向き。
とにかくバンドを愛してる感じがいいです。
6.Goodbye Angels

最後に、5曲目は、Goodbye Angels。
Goodbye Angelsも、アンソニーの実体験に基づいた内容です。
Goodbye Angelsでアンソニーは、傷ついた心をさらけ出しています。
アンソニーの歌詞は、感情の奥底から湧き上がる。
Goodbye Angelsの歌詞は、アンソニーが当時交際していたヘレナ・ヴェスターガードとの別れを題材にしていると言います。
| タイトル | 「グッドバイ・エンジェルス」(Goodbye Angels) |
| 収録アルバム | 『ザ・ゲッタウェイ』(The Getaway) |
| 作曲 | アンソニー・キーディス、フリー、ジョシュ・クリングホッファー、チャド・スミス |
| 演奏メンバー | アンソニー・キーディス(v)、フリー(b)、ジョシュ・クリングホッファー(g)、チャド・スミス(ds) |
| プロデュース | デンジャー・マウス |
聴きどころ
Goodbye Angels聴きどころは、感情の起伏とシンクロする秀逸な楽曲構成にあります。
後半で爆発するフリーの深みのあるスラップにも注目。
アンソニーが描く切ない歌詞を、表現される切なさを、バンドは更に際立たせる。
アレンジがかっこいい。
下記は、The Getaway World Tour前半、2016年7月10日に参加した『T in the Park』のスコットランド公演でのGoodbye Angels。
アンソニーの感情表現にフォーカスした演奏。
大切な存在を失って不安定になった感情の爆発を見事に表現しています。
こちらは、The Getaway World Tour後半、2017年7月27日出演のラトビア公演でのGoodbye Angels。
アンソニーの息子、エヴァリー・ベア・キーディスとの親子共演。
アンソニーが父にしてもらったように、アンソニーも、息子を一人の人間として対等に向き合ってるんでしょうね。
後半、フリーのスラップから流れを正すようにダウンテンポするアレンジが、感情の高ぶりを煽ってきます。
*おまけ*(暴言)
最後はレイカーズ大好きコンビのアンソニー&フリーです。
バスケに対しても超真剣。
2018年10月20日、レイカーズ対ロケッツの試合で選手の乱闘に対し暴言を吐いて観客席から退場させられたアンソニーについて振りかえるフリーのインタビュー動画です。
7.止められない
レッチリは、2012年に「ロックの殿堂(Rock And Roll Hall Of Fame)」入りしました。
そして、今なお、レッチリの進化・深化は止められない。
名実ともに世界最強ロックバンドとなったレッチリの作品が、2010年代の作品です。
I’m With Youは、「手探り」な状況で生まれた作品。
ジョシュの存在感をいかにブレンドするかは、メンバー全員が神経を使ったと思います。
でも、その「手探り」な期間があったからこそ、The Getawayという名作に辿り着いたわけですよね。
まさにMother’s Milkを経て、Blood Sugar Sex Magikが生まれたように。
激推しのDark Necessitiesは、そのような、『時の流れと絆の関係』が顕著に表れていると思います。
是非アルバムを通して楽しんでくださいね。
※下記は「アンソニーの半生=レッチリの歴史」がぎゅっと詰まったアンソニー・キーディス自伝。各メンバーの「出会い」「別れ」「制作の裏側」など、興味深い逸話のオンパレード。めっちゃ面白い。未読の方はぜひ。
レッチリ年代別代表曲
今回は80年代特集でしたが、80年代、90年代、00年代とそれぞれ「レッチリの代表曲とは?【年代別で整理】」にまとめてありますので、下記からどうぞ。
今日は以上です。
skでした。
最後まで読んでくださりありがとうございます!
記事が参考になりましたら幸いです。
※深みを増した極上のグルーヴ
※下記もあわせてどうぞ。
※下記もおすすめです。
Articles : Members of RED HOT CHILI PEPPERS
レッチリ:MEMBERS 記事一覧
sk blog トップページ
Articles : Works of RED HOT CHILI PEPPERS
レッチリ:WORKS 記事一覧
sk blog トップページ
Articles : History of RED HOT CHILI PEPPERS


















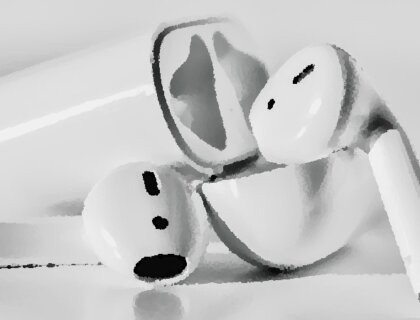



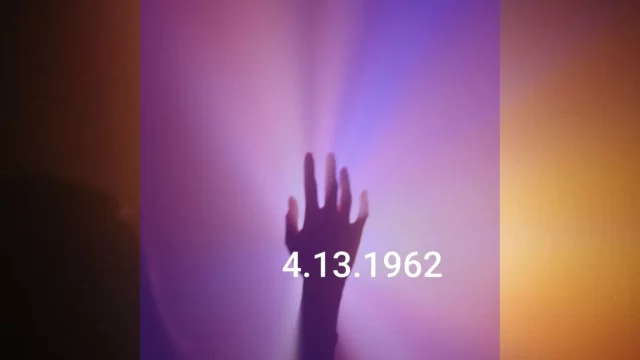


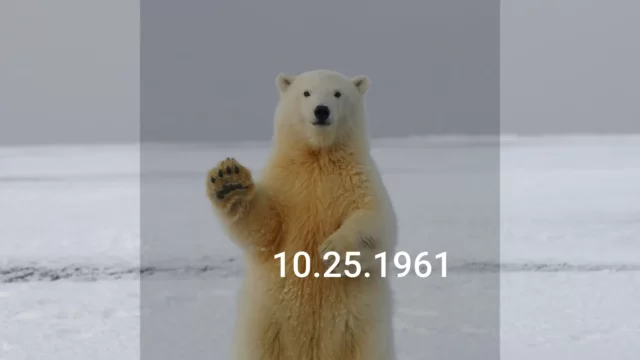






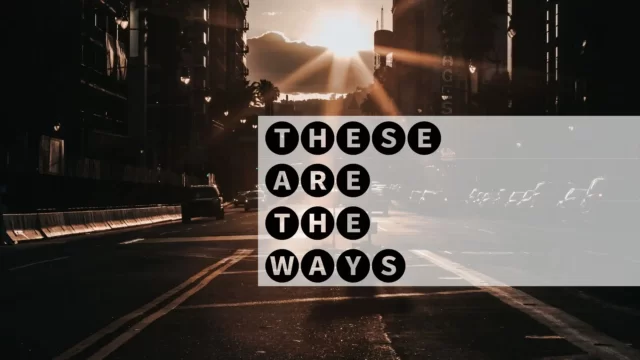








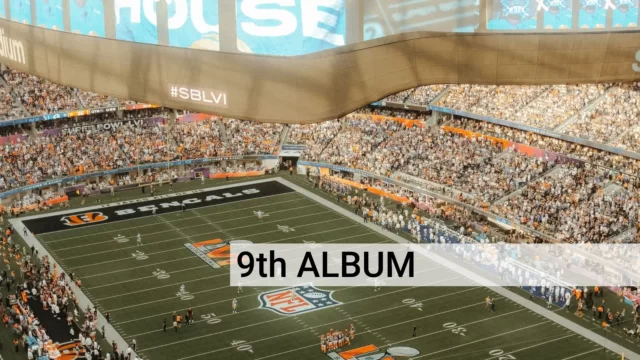


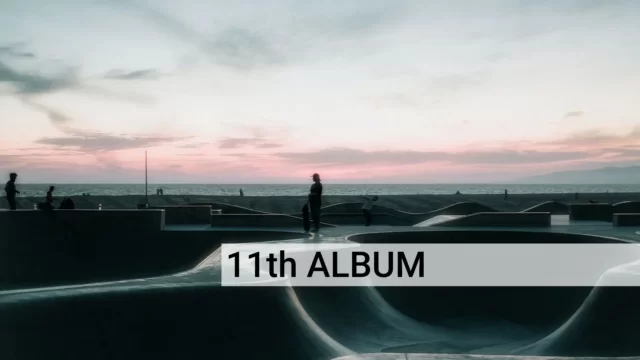

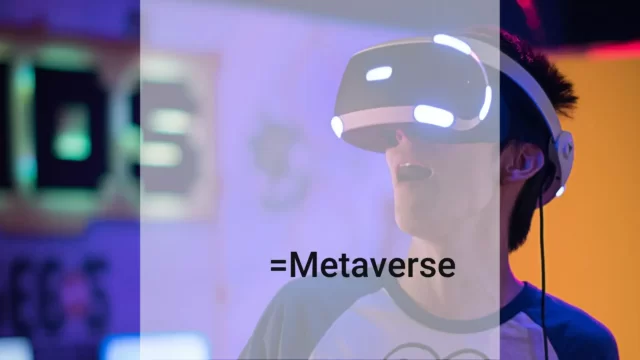
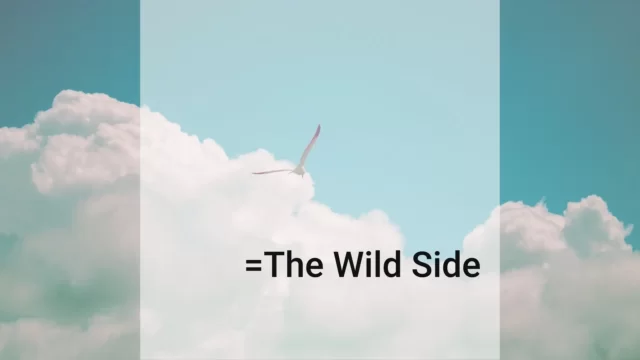
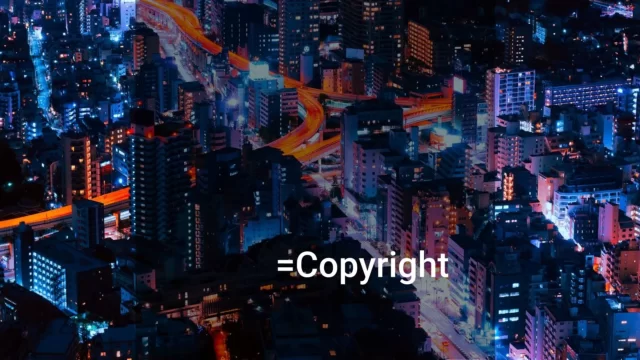



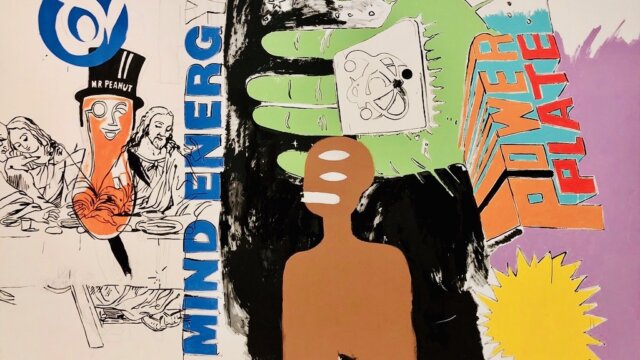











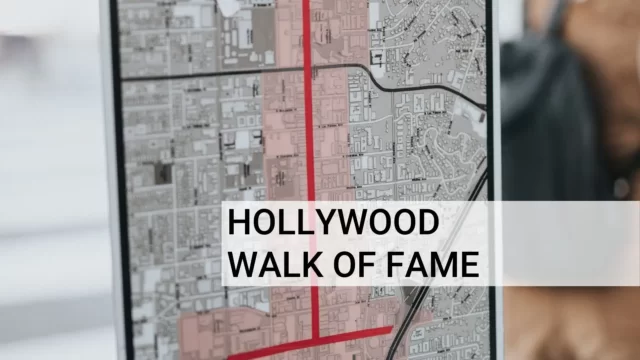






コメント